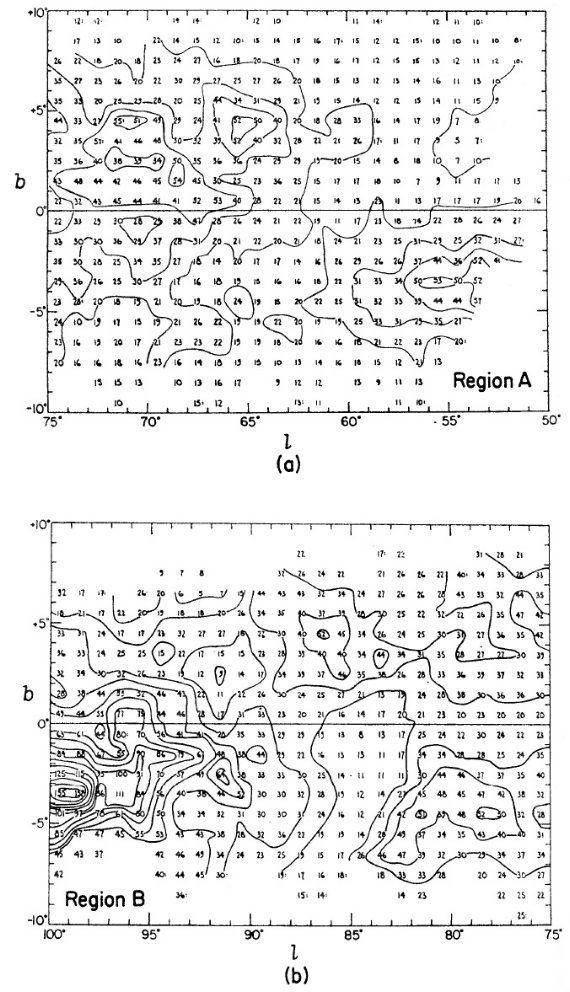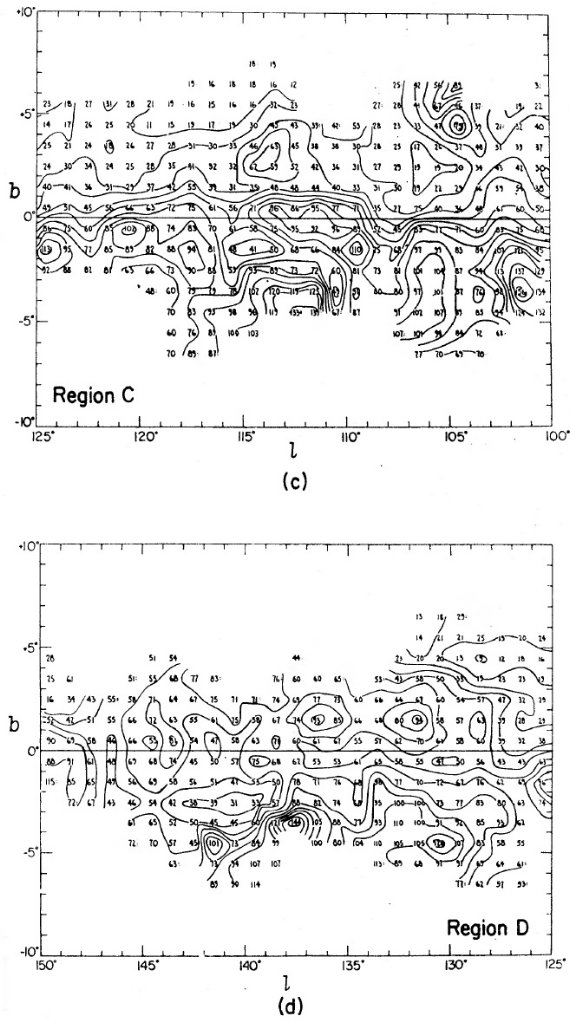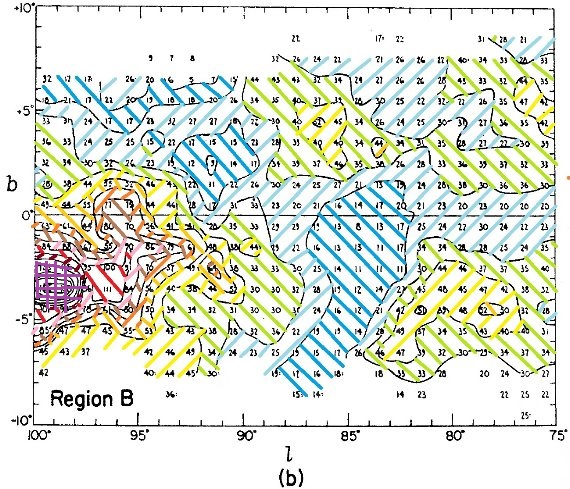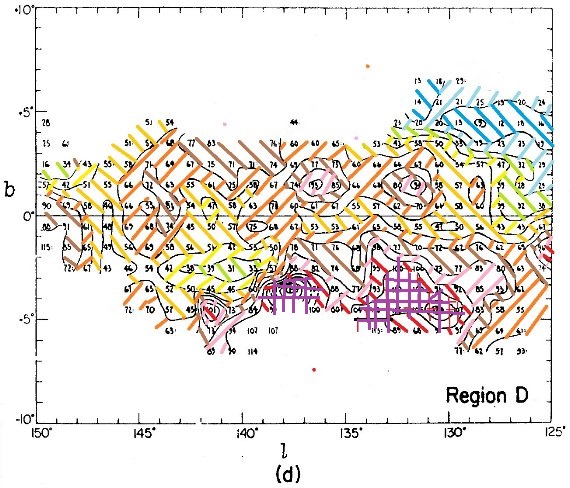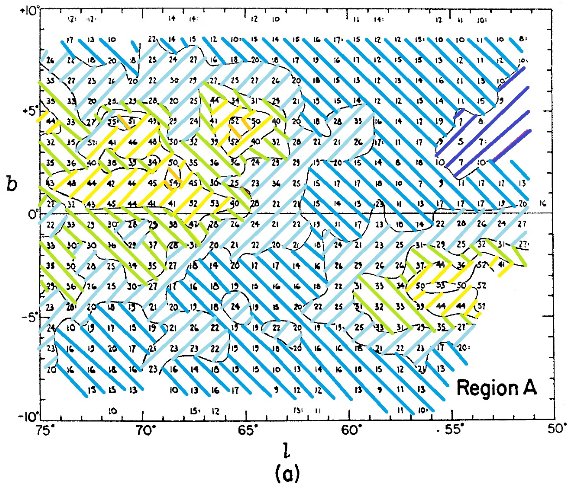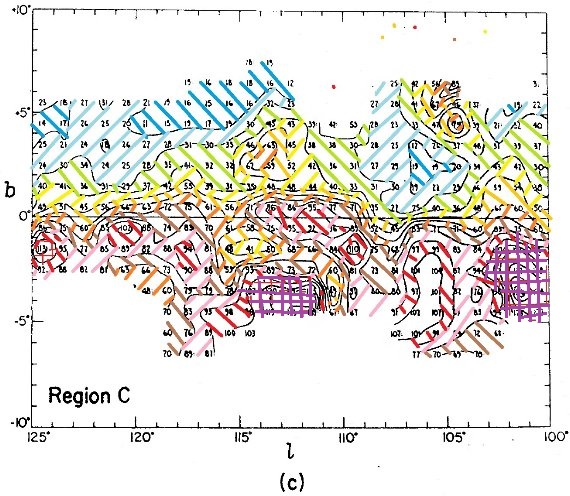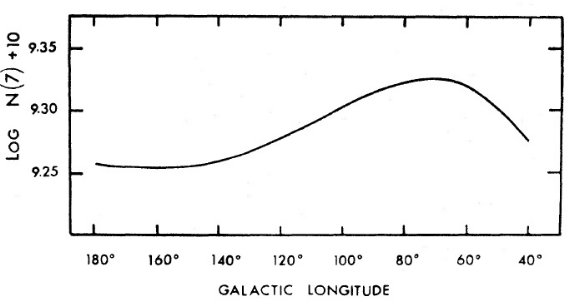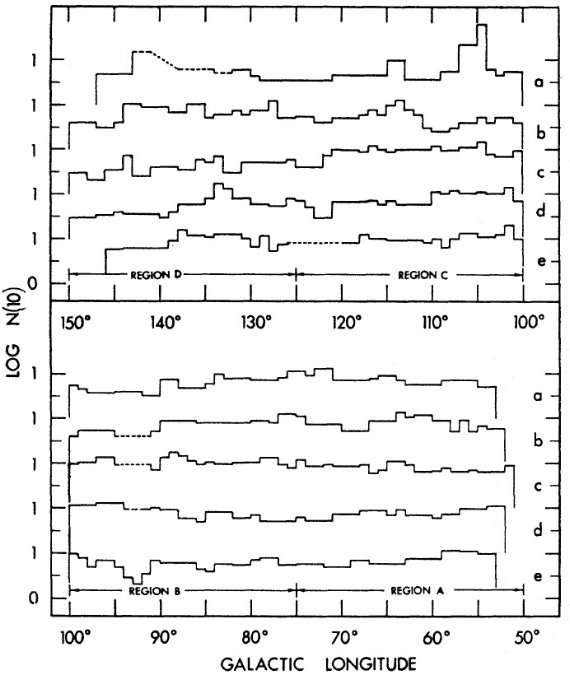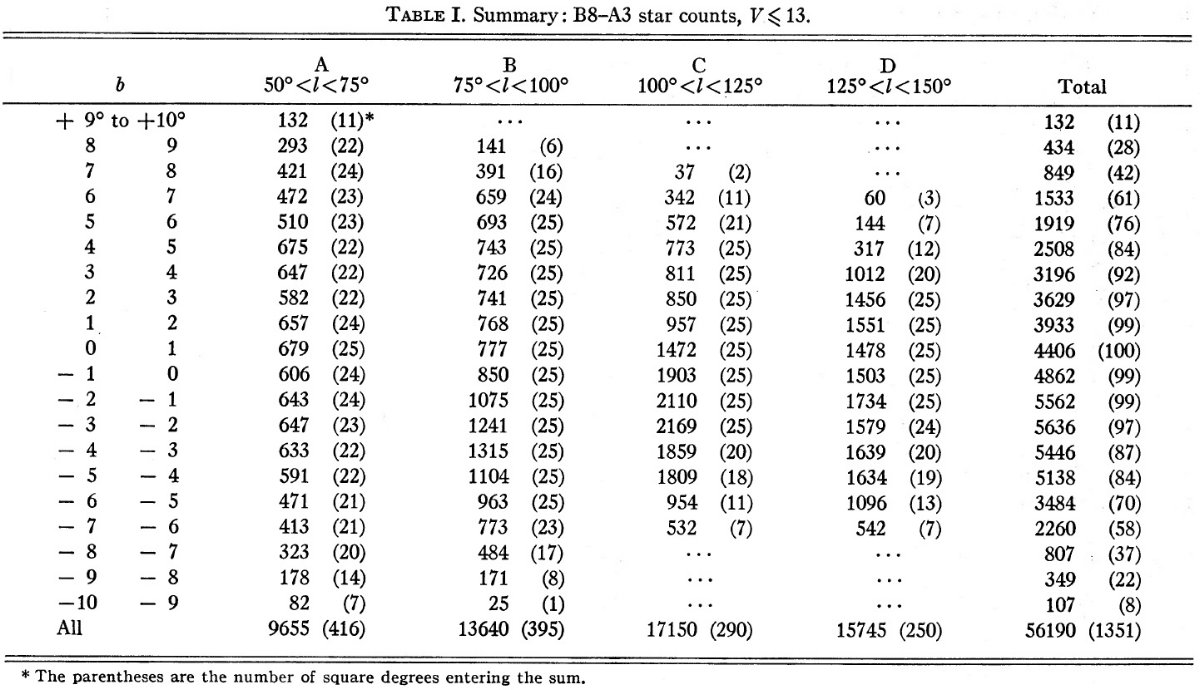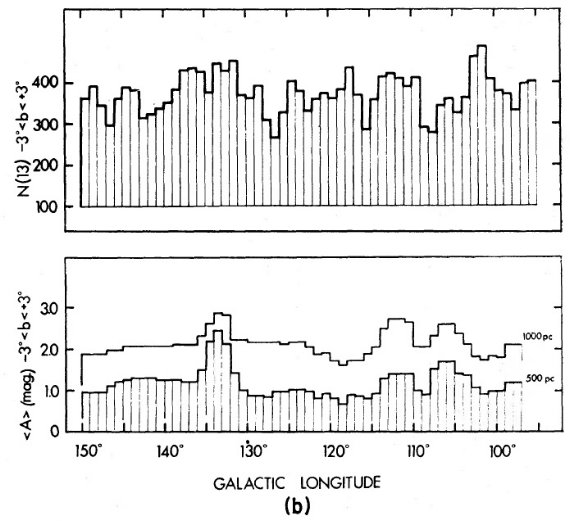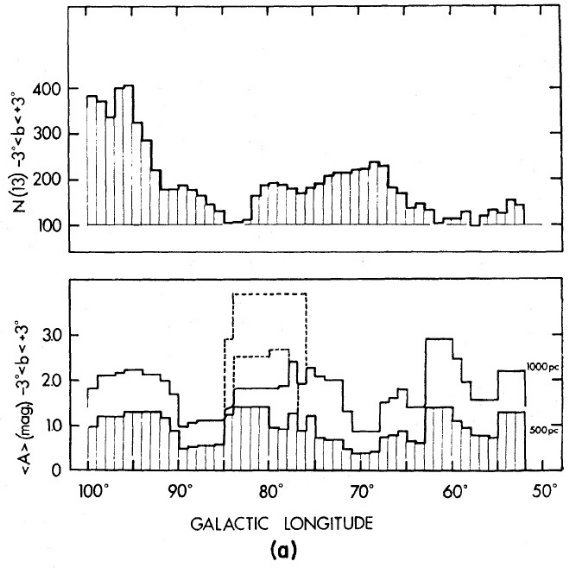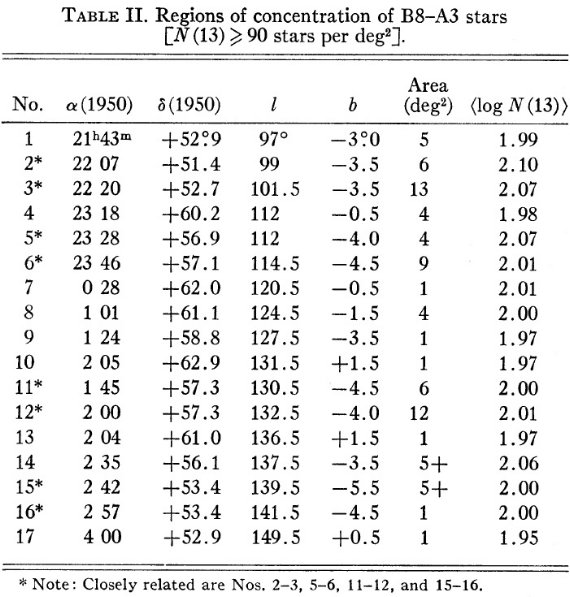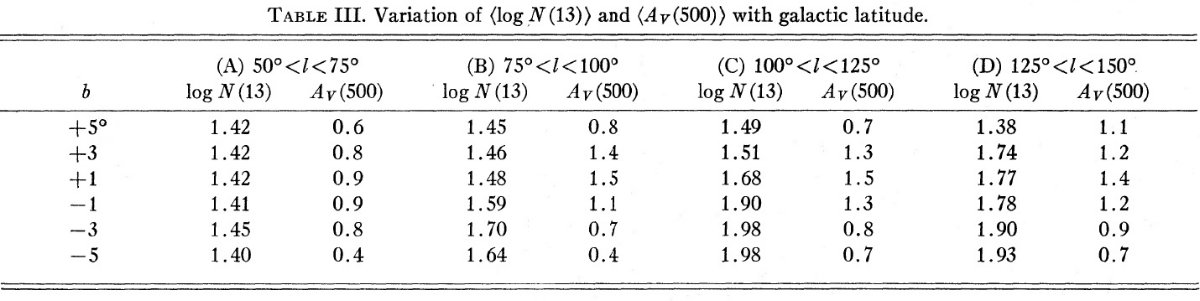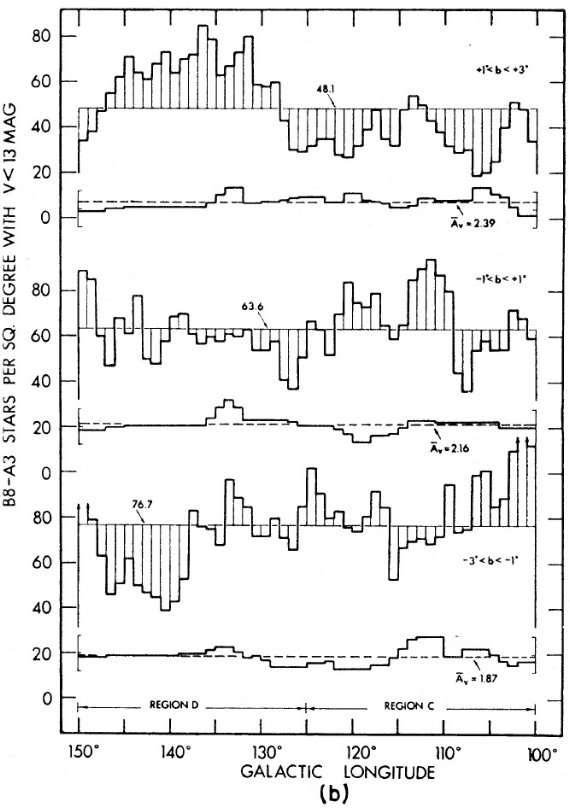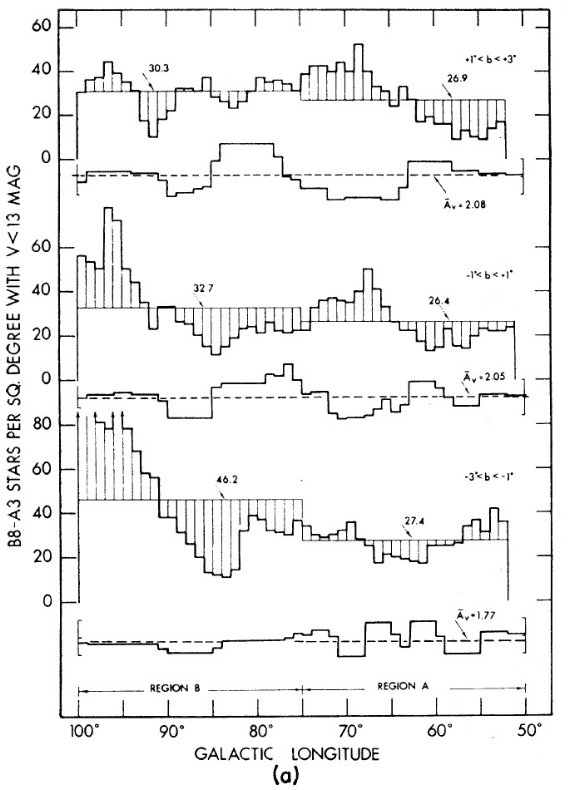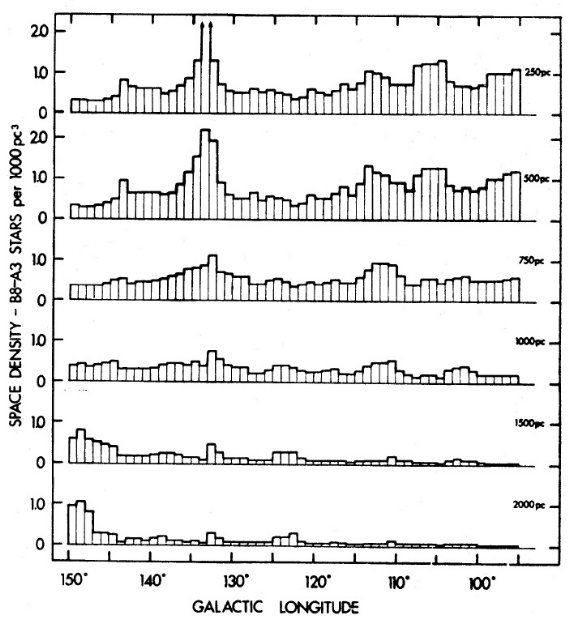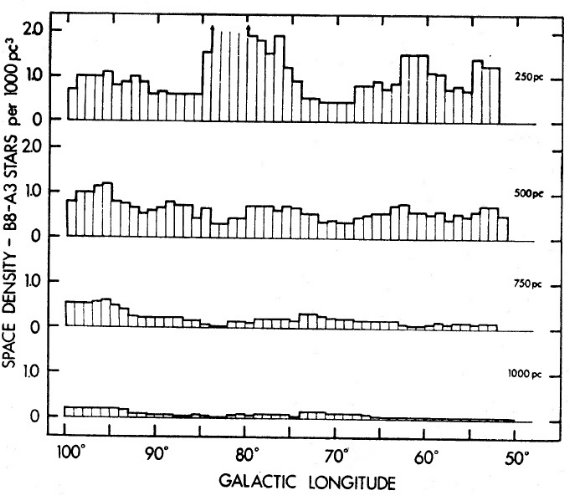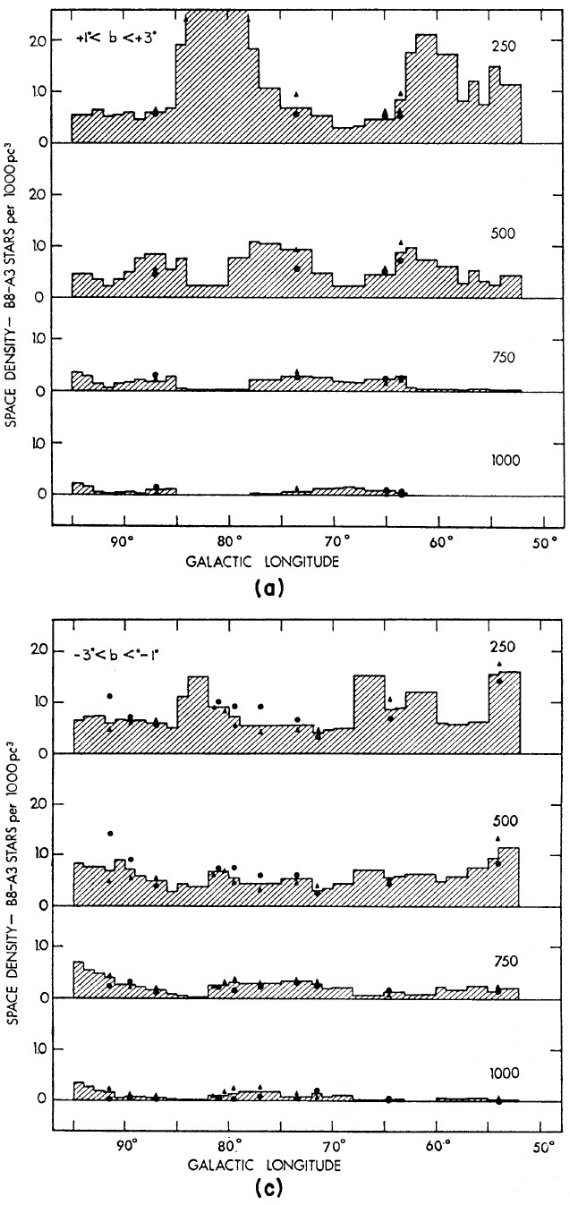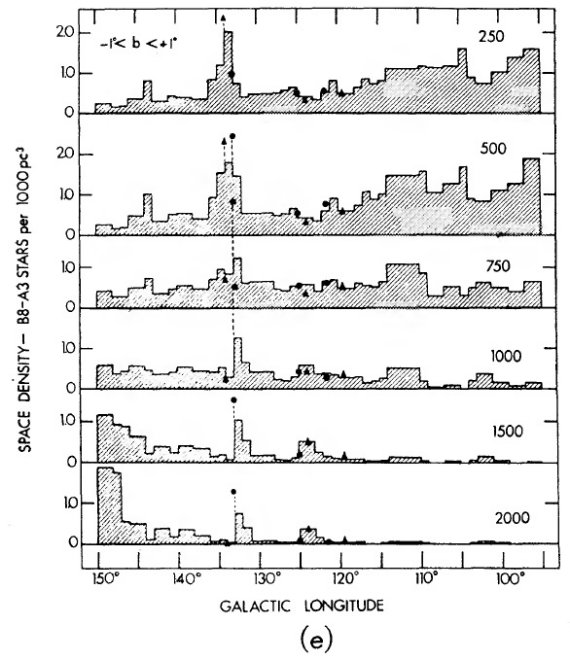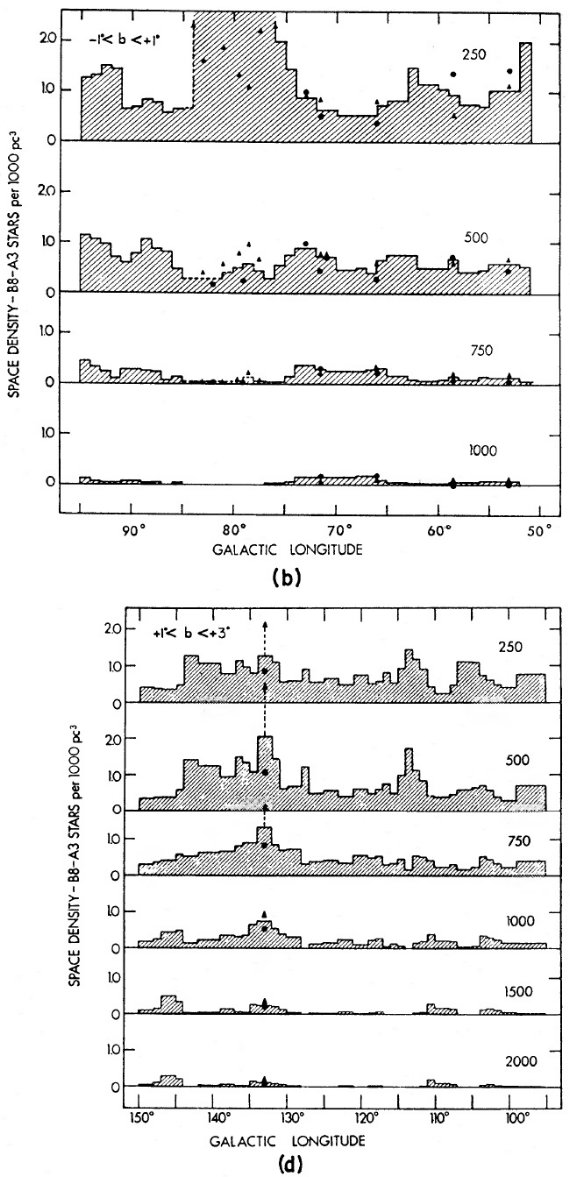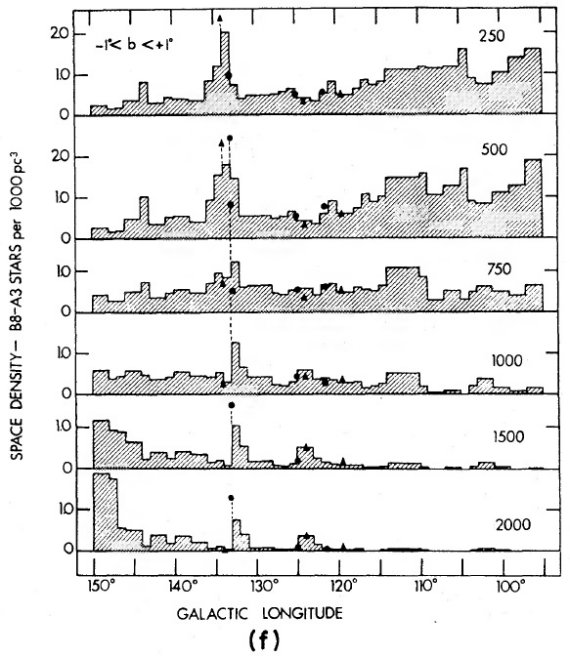D(r) = 空間数密度
N(13), N(10), N(7) を内挿し、N(m) を定め、
A'(m) = [m-1/4, m+1/4] にある 100 deg2 当たりの星数
を求める。星間減光の距離による変化も前に示した文献から得られる。この二つ
から
D(r) = 距離 r における 1000 pc3 当たりの星数
が得られる。
図6=空間密度の(l、r)表示
Mo = +0.9, σ = 0.7 を仮定した。値は Blaauw 1963 から採った。
図6は b = [-3, 3] の平均 D(r) の変化を示す。図には Vulpecula (l = 62),
Cygnus (l = 75 - 85), Cepheus-Lacerta (l = 105 - 115), Cassiopea
(l = 133) 方向の局所的な A-型星の集合が見える。それらは大部分
r < 750 pc である。
| |
図6.B8 - A3 星 b = [-3, 3], r = 250, 500, ... pc での空間密度の銀経変化。
A-型星分布のその他の特徴
A-型星分布のその他の特徴としては、
(i) l = [100, 150], r = 250, 500 pc
D(r) = 0.4
(l = 150) へと緩やかに低下して行く。
(ii) 領域 C,D r > 1000 pc
領域 C,Dでは、r = 1000 pc の先では D(r) が漸減していく。
(iii) 領域 A,B r > 500 pc
領域 A,Bでは r = 500 pc の先で D(r) が急減する。
l = [100, 150], r = 250, 500 pc では D(r) = 1 (l = 100) から
(iv) l > 140, r = [1500, 2000] pc
l > 140, r = [1500, 2000] pc で D(r) が増加する。
|